
銭司遺跡
国道163号を木津川にそって登っていくと、和同開珎の鋳造跡がある。和同開珎は我が国の古い貨幣として知られ、直径25ミリ、和・同・開・珎の4文字が刻まれている。

国道163号を木津川にそって登っていくと、和同開珎の鋳造跡がある。和同開珎は我が国の古い貨幣として知られ、直径25ミリ、和・同・開・珎の4文字が刻まれている。

鷲峰山にある古刹。1300年前に創建され、平安時代の最盛期には50以上の堂宇が建っていたといわれる。鎌倉時代、兵火にあってほとんどの堂宇が消失し、現在は多宝塔だけが往時のおもかげを伝えている。閑...

木津川の流れが聞こえてきそうな場所に建つ祝園神社は、奈良時代、この地にこもった鬼神を鎮めるため、春日大名神を勧請したのが由来といわれている。毎年、一月の申の日から3日間行われるいごもり祭も、鎮魂...

大阪の八百屋半兵衛に嫁いだお千代は、姑に嫌われ実家に帰らされてしまう。庚申の宵に浮かれる大阪生国魂神社の近くで、半兵衛と5ヵ月の子を宿したお千代は心中を遂げる。近松門左衛門の作品「心中宵庚申」の...

創建は和銅2年(709)といわれ、衣食住の神を祀っている。また女性の守り神として婦人の参拝者が多い。毎年8月14日に行われる佐伯灯籠は、貞観5年(859)京都御所清涼殿より灯籠を賜って以来、五穀...

聖徳太子の孫である弓削王の時代に建てられたと伝えられるのみで、詳細は不明。本堂と収蔵庫だけの小さな寺だが、収蔵庫の増長天立像は平安時代のもので、重要文化財に指定されている。

かやぶき屋根の民家が現存していることで名高い美山町だが、特に北村にはそれらが多く集まり、かやぶき屋根の集落が形成されている。のどかな田園風景とかやぶき屋根がマッチして、心がなごむ光景となっている...

本尊に毘沙門天を祀るところから、“蕨の毘沙門さん”の名で知られている。京都鞍馬寺の僧釈峰延が延暦年間(782~805)に開いたといわれ、足利尊氏の帰依を得て以来足利将軍家の祈祷所として崇拝を受け...

南丹市日吉町の中央部にあり、慶雲年間(704~708)の創始と伝えられている。現在の本殿は、宝暦5年(1755)の二間社流造りの建物で、丹波地方最大級の規模を誇っている。また、国の無形民俗文化財...

福知山城は、その前身を「横山城」と呼び、在地豪族横山氏の砦だった。その砦を丹波平定を行った明智光秀が、当時の城郭建築の粋を集めて改築し「福知山城」と改めた。江戸時代には、3層4階の天守閣や広大な...
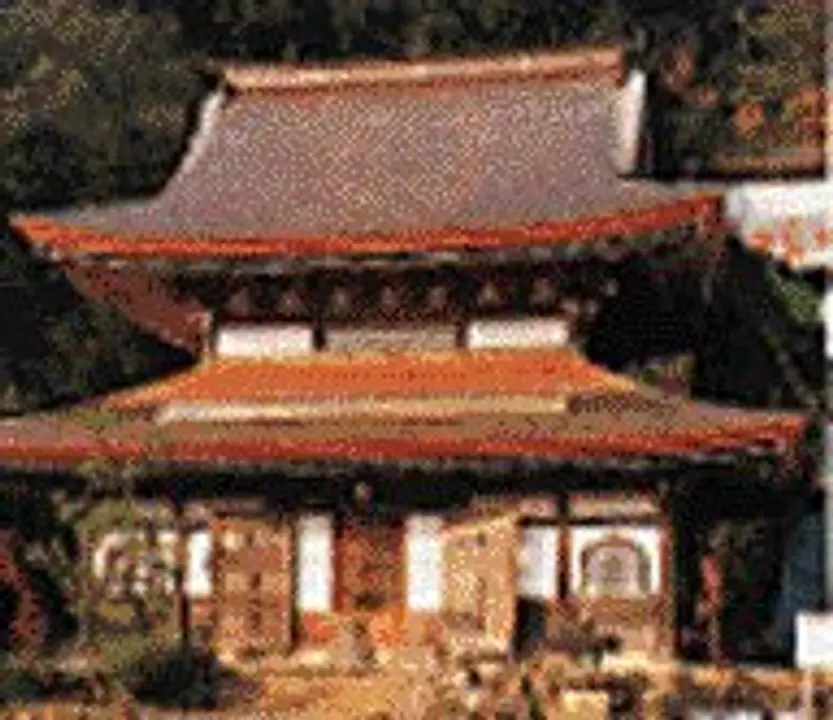
愚中周及が開山した丹波随一の古刹で、古い歴史を刻み、静寂なたたずまいの中にも威厳を漂わせている。本堂は、昭和38年(1963)の再建で、江戸中期~後期建造の開山堂、薬師堂などが境内に昔のままひっ...

奈良時代に行基が創建、のち長徳年中(995~999)に皇慶上人が中興したと伝えられる。本尊は丹後地方最大の丈六仏で、そのおだやかな表情、ふくよかな体つき、やわらかな衣のラインは定朝式を伝える美し...

森鴎外の「山椒大夫」で有名な安寿姫と厨子王丸の悲しい物語の舞台となった舞鶴。三庄(山椒)太夫のもとから逃げ出そうとした安寿姫は、非業の最期をとげたが、土地の人々によって手厚く葬られ、今もその塚が...

俳人与謝蕪村ゆかりの寺。宝歴4年(1754)、蕪村は俳友の竹渓を訪ね、この寺で3年余を過ごして画筆に精進したといわれている。庭に「短夜や六里の松に更けたらず」と刻まれた大きな自然石の句碑や蕪村の...

中世の戦乱を象徴する山城遺構で、平野部を阿蘇海に向けて突き出た標高50mの丘陵上にある。この城は、丹後一色氏の没落の際、最後の攻防がくり広げられた場所で、戦国時代の丹後における代表的な山城のひとつ。

「丹後二の宮」として厚い信仰を集めており、祭神は大宮売神と若宮売神で、平安時代前期の『延喜式』にその名が見える。本殿前の石灯籠2基の右側1基には、「徳治2年3月7日」の刻名があり、鎌倉時代の貴重...

約4km・約2時間阪急京都線西向日駅→史跡長岡宮跡朝堂院跡→史跡長岡宮跡築地跡→北真経寺→史跡長岡宮跡内裏内郭築地回廊跡→史跡長岡宮跡大極殿・小安殿跡→南真経寺→説法石→向日神社(元稲荷古墳)→...

玉川の岸辺に座る数百トンもありそうな岩。その巨岩には、大きさ1mほどの左馬が刻まれており、道行く人を驚かせる。左馬は、女性の習いごと、裁縫や作法、生け花、舞踊を志す人の守り神として、古くから信仰...

笠置山の山頂付近には、花崗岩で造られた巨岩・奇石が多く、その特異な景観から山伏の修行場となっていた。巨岩には、弥勒石、虚空蔵石、文殊石、太鼓石、貝吹岩、ゆるぎ石などがあり信仰の対象となっている。...
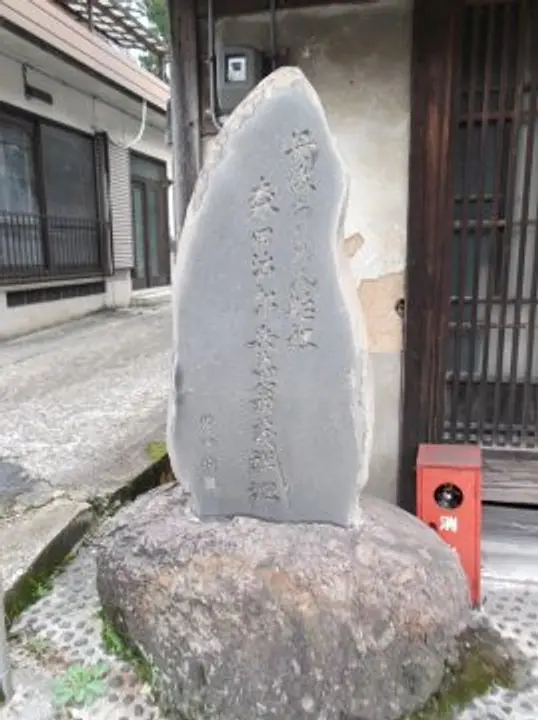
丹後ちりめんが、今日のように独特のしぼを持ち、しなやかな風合いと光沢をもつ織物になったのは、今から約300年前の享保5年(1720)峰山の絹屋佐平治(のちに森田治郎兵衛と改名)が京都西陣の機屋へ...

慶雲元年(704)開基という古刹で、西国第28番札所。本尊は、秘仏の聖観世音菩薩。本道への石段右手にある「撞かずの鐘」は、その音色に鐘を作る際に誤って命を落とした子供の泣き声がするため、鳴らされ...

〈坐禅・法話〉連絡により随時実施。法話。(約40分)定員/50名まで(要予約)坐禅は7月~9月まで電話にて受付。定員/10名まで(要予約)※健脚向き

〈写経と法話〉写経会。おつとめ~法話~写経~粗飯。〈護摩焚きと法話〉不動縁日。護摩焚き~法話。所要時間/約1時間〈写経〉随時実施。9時~15時所要時間/約1時間~1時間30分写経 毎日受付(1名...

バラモン教から伝わり、日本の佛教音楽の元となった声明(しょうみょう)の発祥の地といわれている。〈宿坊〉おつとめ、法話は自由参加。希望により写経(納経料1,000円)有り。定員/約10人(要予約)...